
05/08 (木)更新
今さら聞けない!特定技能介護とは何か?資格条件や仕事内容をやさしく説明
特定技能「介護」は、2019年に施行された在留資格制度で、介護分野における深刻な人手不足を解消することを目的としています。
この制度では、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、介護施設で最大5年間働くことができます。
ただし、訪問介護など一部の業務には従事できません。
また、特定技能「介護」には2号の制度はなく、5年の在留期間終了後は帰国するか、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」に移行する必要があります。
特定技能介護とは何か
 日本の高齢化が進む中、介護業界では深刻な人材不足が続いています。
日本の高齢化が進む中、介護業界では深刻な人材不足が続いています。
こうした背景から注目されているのが、外国人が日本の介護現場で働くことを可能にする「特定技能介護」という在留資格制度です。
しかし、「特定技能介護って何?」「技能実習やEPAとはどう違うの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
このセクションでは、制度の基本概要や導入の背景、働ける仕事内容、今後の展望、他制度との違いまでをやさしく丁寧に解説します。
特定技能介護を目指す方にとって、制度の全体像をしっかりと把握する第一歩として役立ててください。
特定技能介護の概要
「特定技能介護」は、2019年に新設された在留資格「特定技能1号」の一分野として位置づけられており、一定の専門性と日本語能力を有する外国人が、日本国内の介護業務に従事することを可能にする制度です。
この資格を取得することで、最長5年間、日本の介護施設などでの就労が認められます。
制度の特徴として、直接雇用が原則であること、そして訪問介護の業務には従事できないことが挙げられます。
また、特定技能介護には現時点で「特定技能2号」が存在していないため、より長く日本で働き続けたい場合には、介護福祉士資格の取得が必要になります。
詳しくは、公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)の特設ページもご参照ください。
👉 出入国在留管理庁「特定技能:介護」詳細ページ(JICWELS)
制度の背景と目的
特定技能介護の制度は、日本国内の急速な高齢化と介護人材不足に対応するために導入されました。
介護分野では日本人労働者だけでは需要を満たすことが難しくなっており、外国人材の受け入れが社会的にも必要とされるようになっています。
この制度は、短期的な人手補充ではなく、一定の教育や試験を通過した人材に、現場で継続的に活躍してもらうことを目的としています。
特定技能介護の対象職種
特定技能介護で従事できるのは、介護施設における身体介助、食事・入浴・排せつなどの日常生活の支援、レクリエーション補助、記録業務などが主な業務です。
一方で、訪問介護や医療行為を伴う業務は対象外とされており、あくまで「施設内の介護サービス」が活動の範囲となります。
今後の展望
現在、特定技能介護には「2号」制度がないため、5年間が在留期間の上限です。
しかし今後の人材ニーズの高まりや制度の整備状況によっては、制度の見直しや延長の可能性もあります。
さらに、在留期間中に介護福祉士国家試験に合格すれば、「介護」ビザへ移行できるため、長期就労・永住への道も開かれます。
他の制度との違い
技能実習制度との大きな違いは、「転職が可能」である点です。
技能実習では原則として同一機関での就業が求められますが、特定技能介護では、契約終了後に条件を満たしていれば転職が可能です。
また、EPA(経済連携協定)との違いは、より実務重視で制度設計されていることです。
EPAでは日本語の習得が重視されますが、特定技能は「就業即戦力」が前提で、試験に合格すれば比較的早期に働き始められるのが特徴です。
特定技能介護とは、介護分野に特化した在留資格であり、日本の人材不足を背景に、外国人労働者が実務の担い手として期待されています。
制度の特徴や就業条件、他制度との違いを正しく理解することで、自分に合った働き方や将来設計を見据えた準備が可能になります。
今後、制度の拡充やキャリアパスの明確化が進めば、さらに多くの方にとって有望な選択肢となるでしょう。
特定技能介護の資格取得要件
特定技能「介護」分野で働くためには、単に「働きたい」という意思だけでなく、一定の知識・技能・日本語能力を証明する資格の取得が求められます。
これらの要件は、すでに介護職に就いている外国人材や、これから日本で介護のキャリアを築こうとする方にとって、明確な道しるべになります。
この章では、特定技能介護に必要な資格、試験の種類や準備、学歴や実務経験に関する要件などをわかりやすく整理し、申請に必要な書類についても触れていきます。
詳細な制度内容は 出入国在留管理庁の公式資料や JICWELSの公式サイトでも確認可能です。
必要な資格と条件
特定技能介護の在留資格を取得するには、以下2つの試験に合格する必要があります。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験(もしくは日本語能力試験N4以上)
この2つに合格すれば、日本の介護事業所で特定技能1号介護として最大5年間の就労が可能になります。
なお、他の在留資格(たとえば技能実習など)からの移行者は、一定条件下で試験免除となるケースもあります。
技能試験の内容と準備
介護技能評価試験は、ベッドメイキングや移乗・移動の介助、バイタルチェックといった基本的な介護技術を問う内容となっており、実技と筆記(選択式)の両面から評価されます。
試験対策は、厚生労働省やJICWELSが提供する過去問やテキストを活用することで、効果的に準備を進めることが可能です。
試験日程や申込方法は、JICWELSの介護技能評価試験ページ をチェックしておくとよいでしょう。
介護日本語試験の重要性
「介護日本語評価試験」では、介護現場で使われる専門的な日本語を理解できるかが問われます。
試験に合格することで、現場での円滑なコミュニケーションが取れると評価され、日本語能力試験(JLPT)N4以上と同等の扱いになります。
介護分野は特に利用者との言葉のやり取りが重要なため、語学力の強化は避けて通れない要素です。
必要な経験年数と学歴
特定技能介護に関しては、実務経験年数や学歴の要件はありません。
つまり、介護の専門学校を出ていなくても、未経験であっても、試験に合格すれば在留資格を取得して就労が可能です。
ただし、日本語の習得状況や生活習慣への適応力も重要になるため、計画的な準備が求められます。
申請書類のチェックリスト
資格要件を満たした後に必要なのが、在留資格「特定技能1号(介護)」の申請です。
以下が主な提出書類の一覧です。
- 介護技能評価試験の合格証明書
- 日本語評価試験またはJLPTの合格証明書
- 雇用契約書(直接雇用が条件)
- 支援計画書(受入機関が作成)
- 住居・生活支援体制に関する説明書
- パスポートのコピー、履歴書など
詳細は 特定技能関係の申請・届出様式一覧に掲載されています。
特定技能介護の資格取得には、試験合格と基本的な日本語能力の証明が欠かせません。
しかし、実務経験や専門学歴は問われないため、介護職を目指す外国人にとって門戸が広く開かれた制度といえるでしょう。
試験日程の確認や制度の最新情報は、JICWELS(公式サイト)や 出入国在留管理庁の情報をこまめに確認することをおすすめします。
特定技能介護の申請手続き
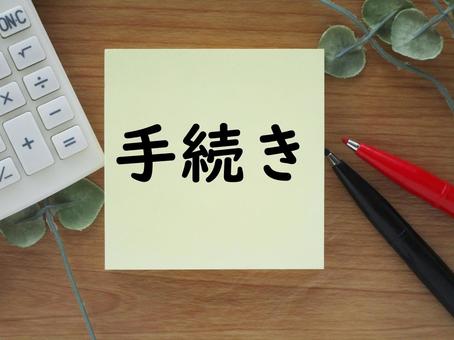
特定技能「介護」分野での在留資格を取得するには、正確な手続きと書類準備が欠かせません。
特に外国人本人だけでなく、受け入れ機関側にも適切な対応が求められるため、申請前に全体の流れを理解しておくことが重要です。
ここでは、申請の流れから必要書類、注意点、オンライン申請のポイントまで詳しく解説します。
申請の流れと手順
- 外国人が必要な試験(介護技能評価試験・日本語能力試験など)に合格
- 雇用先企業と雇用契約を締結
- 雇用主が「支援計画書」などを含む必要書類を準備
- 出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」または「変更申請」を行う
- 審査を経て在留資格認定証明書が交付される
- 本人が日本大使館で査証(ビザ)を取得
- 日本に入国後、就労を開始
必要書類の詳細
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書・雇用条件書
- 支援計画書(外国人支援を行う体制の書類)
- 技能試験合格証明書
- 日本語能力証明書(N4以上または介護日本語評価試験合格証)
- 健康診断書
- パスポートのコピー
- 顔写真(4cm×3cm)
- 雇用機関の登記事項証明書
- 組織概要書類、直近の決算書類 など
これらの書類の最新様式と記入例は、出入国在留管理庁の公式ページで確認可能です。
👉特定技能 申請・届出様式一覧(出入国在留管理庁)
申請時の注意点
- 申請書類は全て正確かつ最新のものを提出する必要があります。
- 支援計画書に記載する内容は、現場で実施可能な支援内容であること。
- 派遣雇用は禁止されているため、受け入れ機関との直接雇用が必須。
- 申請内容や企業情報に不備があると審査に時間がかかる、または却下される場合もあります。
申請のタイミングと期間
- 申請は、雇用契約締結後すぐに手続き可能。
- 審査期間は平均1〜3ヶ月程度ですが、混雑状況により前後します。
- 日本国内からの「在留資格変更」申請と、海外からの「認定証明書交付申請」で手続きが異なるため、タイミングの把握が重要です。
オンライン申請方法
2022年より、特定技能の一部申請がオンラインで可能になりました。
- 申請は「出入国在留管理庁オンライン申請システム」から行います。
- 事前にID申請と登録が必要。
- 必要な添付書類はPDF形式で提出し、原本は後日郵送または提示を求められる場合があります。
申請成功のカギは「準備と確認」
特定技能「介護」の申請では、試験の合格・正しい書類の準備・タイミングの管理が成功のカギです。
手続きは複雑に見えますが、公的機関の情報を正確に読み取り、計画的に準備を進めれば確実に前進できます。
不安がある場合は、専門家や行政書士に相談するのも有効な手段です。
特定技能介護で働くための準備

特定技能「介護」で働くには、在留資格の取得だけでなく、実際の就職活動や職場環境への適応準備も重要です。
日本で安定して長く働くためには、単に試験に合格するだけではなく、日本語力や文化への理解、そして介護という仕事に対する心構えも求められます。
ここでは、外国人介護士として安心してスタートを切るための準備ポイントを5つに分けて紹介します。
就職活動のポイント
就職活動では「特定技能介護」を受け入れている施設かどうかをまず確認しましょう。
ハローワークや特定技能に対応している求人サイトを活用すると効率的です。
また、支援機関と連携して就職先を紹介してもらうのもひとつの手です。施設の規模や支援体制も事前にチェックしておきましょう。
面接対策と履歴書作成
面接では、「なぜ日本で介護の仕事をしたいのか」という動機が重視されます。
自分の経験や介護に対する思いを日本語で簡潔に話せるよう準備しましょう。
履歴書は日本の形式に合わせて作成することが必要で、写真貼付や手書きの場合もあります。
支援機関にチェックしてもらうと安心です。
職場での日本語能力向上
介護現場では利用者とのコミュニケーションが非常に重要です。
特定技能介護ではN4以上の日本語力が求められますが、実際にはN3〜N2程度の会話力があると働きやすくなります。
仕事でよく使われる言葉(例:排泄、食事、移乗など)をあらかじめ勉強しておくとスムーズです。
文化理解と適応
日本の職場文化には「報連相(報告・連絡・相談)」が重視され、チームワークが非常に大切です。
また、日本では時間厳守や丁寧な言葉づかいも重視されます。
文化の違いに戸惑うこともあるかもしれませんが、事前に日本の習慣を学ぶことで不安を減らせます。
地域イベントやボランティアに参加するのも効果的です。
介護現場での心構え
介護は体力的にも精神的にもハードな仕事です。ときには認知症の方の対応や、排泄介助なども行います。
そのため、「人の役に立ちたい」という思いと同時に、ストレス対策や体調管理の意識も必要になります。
仕事を続けるうえで、自分のメンタルや体力をどう守るかも重要な準備です。
現場で輝くために、今からできることを
特定技能介護の資格を取得したあとは、実際に働き始める準備が成功のカギを握ります。
日本の文化・言葉・仕事への理解を深めることで、よりスムーズに働き始めることができます。
就職活動の段階から意識を高め、現場で信頼される人材を目指しましょう。あなたの優しさと努力が、日本の介護現場に必要とされています。
特定技能「介護」で働く際に知っておくべき注意点とルール

特定技能「介護」は、外国人が日本で介護職として就労できる貴重な制度ですが、他の在留資格とは異なる制限やルールがいくつかあります。
これらを知らずに働き始めると、思わぬトラブルやルール違反につながる可能性も。
ここでは、特定技能介護で働く前に必ず知っておきたい重要なポイントをわかりやすく解説します。
特定技能では派遣社員として働けないので注意
特定技能介護の在留資格では、労働者派遣の形態は禁止されています。
つまり、派遣会社に雇用されて、別の施設に派遣されるという働き方はNGです。原則として、就労先の施設と直接雇用契約を結ぶ必要があります。
この点は、介護施設選びの際にもよく確認するようにしましょう。
訪問介護の仕事には従事できない
特定技能介護の対象業務は、施設内での介護業務に限定されます。
そのため、ヘルパーとして利用者の自宅を訪問する「訪問介護」は行えません。
訪問介護は日本人介護士でも要件が厳しく、外国人には在留資格の制限により認められていないため、職種選びには注意が必要です。
受け入れ可能な人数には上限がある
介護事業所が特定技能外国人を受け入れるには、事前に受入計画の提出と認定が必要です。
そして、日本人職員の数に応じて受け入れ可能な人数にも上限が定められています。
つまり、「希望すれば何人でも雇える」わけではないため、就職先によっては定員に達している場合もあります。
技能実習と違って転職は可能!その条件とは?
特定技能介護は、技能実習制度と違い、他の事業所への転職が可能です。
ただし、転職の際には新しい受け入れ先でも在留資格の更新手続きが必要となるため、転職先の体制や支援内容を慎重に確認することが大切です。
転職を希望する場合は、登録支援機関などのサポートを受けると安心です。
介護職には特定技能2号の制度が存在しない
多くの分野で、在留期間の延長や家族の帯同が可能となる特定技能2号への移行が認められていますが、介護分野には現時点で「2号」が存在しません。
つまり、特定技能1号で最長5年間働いたあとは、介護福祉士の国家資格を取得して別の在留資格に変更する必要があります。
長期的に日本で働き続けたい方は、早めに資格取得を目指す計画を立てることが重要です。
制度のルールを正しく理解して安心して働こう
特定技能介護制度には、派遣不可や訪問介護の制限、在留期間の上限など、特有のルールがあります。
これらを正しく理解することで、働き始めた後に「知らなかった…」というトラブルを防ぎ、より安心して就労生活をスタートできます。
あなたのスキルと熱意が、日本の介護現場で活かされるよう、制度の枠組みもしっかり把握しておきましょう。
特定技能介護でのキャリアと展望

特定技能「介護」は、単なる一時的な働き口ではありません。
制度を正しく理解し、自身のキャリアと照らし合わせて行動すれば、将来の道を大きく広げることができます。
ここでは、特定技能介護から始まるキャリアの可能性や、スキルアップの方法、将来的な展望について詳しく見ていきましょう。
キャリアパスの可能性
特定技能介護で一定期間働くことで、日本の介護現場での実践経験が蓄積されます。
この経験は、将来的に介護福祉士の国家資格を目指すうえで非常に有利に働きます。
介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更でき、より長期間にわたる就労とキャリアアップが可能になります。
さらなる資格取得とスキルアップ
キャリアアップを目指すうえで欠かせないのが、日本語能力の向上と介護に関する専門知識の習得です。
日本語については、JLPT(日本語能力試験)N2以上を目指すことが推奨されており、利用者やスタッフとの円滑なコミュニケーションに不可欠です。
また、介護職員初任者研修や実務者研修などのステップを踏んで、国家資格である介護福祉士取得への道を築くことが重要です。
長期的なキャリアプラン
特定技能1号では最長5年間の在留が可能ですが、その先を見据えたプランを早めに立てることが成功のカギです。
多くの方が、5年の間に介護福祉士資格を取得して「介護」在留資格に切り替え、日本での長期就労や永住申請を目指しています。
また、介護現場での経験をもとに、将来的に管理職や教育指導のポジションを目指すことも現実的な選択肢です。
労働環境と待遇改善
近年、外国人介護職に対する待遇改善や労働環境の見直しが進んでいます。
特定技能介護で働く方々にとっても、適切な給与水準・休暇制度・福利厚生などの整備が進められている施設を選ぶことが重要です。
日本政府も、外国人材の定着を図るため、支援体制の整備を強化しています。
帰国後のキャリア選択
5年間の就労を経て帰国する場合でも、日本での介護経験は国際的に高く評価されるスキルとなります。
母国で介護関連の指導者や施設運営者として活躍したり、日本語力を生かして日本企業で働いたりと、多様なキャリアの選択肢が広がるのも特定技能介護のメリットです。
介護の仕事は“今”だけでなく“未来”をつくるステップに
特定技能介護は、単なる就職ではなく、未来を見据えたキャリアの出発点です。資
格取得や経験の蓄積によって、日本でも母国でも、より良い仕事と生活のチャンスを手にすることができます。
目の前の仕事に真剣に取り組みながら、数年後の自分を想像し、積極的にステップアップを目指しましょう。
特定技能介護のポイントを振り返って:安心して次のステップへ進むために

特定技能「介護」という制度は、外国人が日本で介護の仕事に就くための新しい道を開くものです。
資格取得に必要な条件や試験の内容、申請手続きの流れ、そして働く上での注意点まで、しっかり把握することで不安を軽減し、自分の可能性を前向きに捉えることができます。
この制度を活用することで、日本での就労だけでなく、介護福祉士へのステップアップや帰国後のキャリア形成にもつながる可能性があります。
今の自分に必要な準備は何か?どんなキャリアを描きたいのか?
この記事を通して考えるきっかけとなり、「自分にもできるかもしれない」から「自分にもできる!」という自信へとつながることを願っています。
関連記事一覧
SELECT人気記事一覧
まだデータがありません。





